
1. 法定雇用率という“ノルマ”
障害者雇用は「社会貢献」だと言われる。
でも現実は義務だ。
法定雇用率を下回れば企業は納付金を取られる。
達成すれば減免される。
だから企業は枠を埋める。
それだけだ。
助成金も出る。
一人雇うごとに、国から金が入る仕組み。
「社会参加の促進」って建前は立派だが、
企業からすれば人件費を相殺できる補助金だ。
誰も「生活を支えよう」なんて言ってない。
「経費を削減しろ」「国の罰金を回避しろ」。
それが障害者雇用の動機だ。
2. 「配慮します」=「単純労働」
求人票には「合理的配慮します」って書く。
でも中身は「誰でもできる仕事を与える」だけ。
企業はリスクを避ける。
教えなくても済む、任せきりにできる作業を切り出す。
思考力も判断力も不要なライン作業、データ入力、清掃。
それを「適正な配慮」と呼ぶ。
工夫の必要な業務は回さない。
成長を前提にした教育もしない。
昇進試験も除外される。
「ミスが怖いから」
「負担をかけたくないから」
結果、当事者はキャリアを築けない。
3. 「週20時間」で人件費を最適化
企業にとってフルタイム雇用はリスクだ。
社会保険料の負担が重くなるし、
解雇規制も厳しい。
だから「週20時間」のパート扱いで雇う。
社会保険加入の義務を外せる。
体調への配慮って言えば聞こえはいい。
でも実態はコスト管理だ。
障害者雇用の成功事例で出てくるのは
「週20時間で無理なく長く働けてます」。
そりゃ企業からすれば理想形だろう。
補助金をもらえて、低賃金で回せて、解雇の心配もない。
4. 「正社員登用あり」の建前
求人票に「正社員登用あり」と書くのは自由だ。
制度を用意しておけば「機会を平等にしてる」ことになる。
でも実際に試験を受けさせるのは
コミュ力が高くて、障害を感じさせない人間だけ。
合理的配慮を必要とする人は対象外。
企業は言い訳ができる。
「門戸は開いていた」
「本人の問題だ」
法をクリアする体裁は整う。
でも障害者側から見れば、正社員登用は絵空事だ。
希望を持たせておいて、現実は非正規の壁の中。
5. 「支援」は企業のリスク管理
合理的配慮、就労移行、定着支援。
全部「障害者を守る仕組み」って言われるけど、
実態は「企業のリスクを減らす仕組み」だ。
支援員は問題を潰すために動く。
「辞められると雇用率が下がる」
「トラブルは困る」
だから本人の希望より「波風立てない調整」を優先する。
企業も「支援してます」と言える。
国も「雇用率達成」と胸を張れる。
数字は伸びる。
助成金は出る。
納付金は減る。
その裏で、週20時間、時給1000円以下で
将来設計も立たない生活を送る当事者が増える。
でも誰も責任は取らない。
「障害者雇用は社会貢献だ」
言葉は綺麗だが、現実はコストカットの仕組みだ。
そのことを一番知っているのは、毎月ギリギリで暮らしてる俺たちだ。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

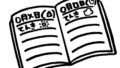

コメント