こんにちは。
今日は発達障害者の視点から見た障害者の雇用上の問題について書きます。
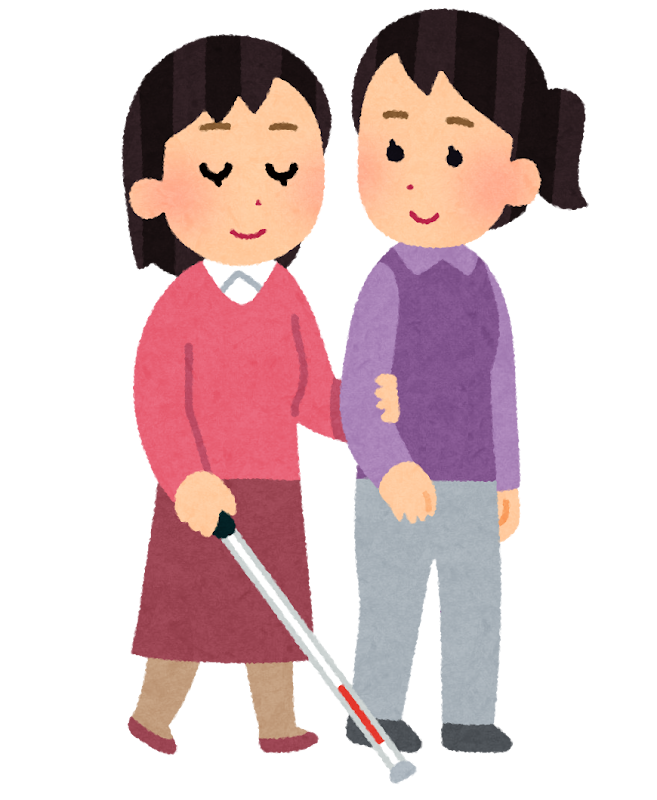
職場や上司の理解不足
発達障害だけでなく精神障害者にも言えることですが、発達障害は目に見えない障害のため、周囲からの理解や配慮を得られにくいです。
パッと見ただけでは健常者か発達障害かの区別はつきません。区別が付くとしたら、二次障害で重度のうつ病や双極性障害があり、症状が強く出ている場合などでしょう。
障害者に見られるかどうかは日常生活上ではそれほど問題になりにくいですが、問題はこれが仕事になった時です。
多くの発達障害の方は、障害の特性ゆえに仕事上の困りごとが見られます。例えば相手の話を文字通りにしか受け取れないとか、聞いたことをすぐに忘れてしまうなどです。
ですが、それらの特性は見た目では分かりませんから、発達障害のことをよく知らない健常者から見たら、「全然仕事ができない」とか、「使えない奴」というレッテルを貼られやすいのです。
もっと言うと、障害特性が原因で仕事ができないとしても、「能力不足」が原因で仕事ができない、という理解をされやすいのです。
適切な伝え方や配慮をすればきちんと働いてもらえる方であっても、職場や上司、同僚の理解がないと業務のミスマッチや不適切な指導につながることになります。
そこからストレスが溜まりうつ病などの二次障害になって働けなくなるパターンや、職場の人間関係トラブルが起きて退職を余儀なくされるパターンをたくさん見てきました。
発達障害の方が社会で働くにあたり、周囲の理解というのは非常に重要な要素の1つです。
そもそも職場に障害のある方を受け入れよう、理解しようという風土がないと障害者、特に精神障害や発達障害の方は居づらいと思います。
業務内容のミスマッチ
職場の理解と並んで障害者が働く上で問題となりやすいのが業務内容のミスマッチです。
たとえば得意な分野では健常者並み、もしくは同世代の中でも頭1つ抜けて得意な方だったとしても、「発達障害だから」と言う理由で簡単な業務しか任せてもらえない。
または得意な業務と苦手な業務の個人差が大きいのに、苦手な業務も得意な業務と同じレベルで遂行することを求められる、などです。
これは特に発達障害の人が働く上で困りやすいポイントの1つでもあります。発達特性から得意不得意の差が大きいのが発達障害なのに、画一的な業務遂行を求められてしまうのです。
業務内容のミスマッチを防ぐには、採用段階で会社側に十分な障害理解をしてもらうか、入社後指導者や配属先の部署とよく話し合って何が得意で、何が不得意かを知ってもらう必要があります。
しかし、実際にはそこまで細かい配慮がなされることの方が少なく、誰でもできる仕事を延々とやらされるか、全ての業務を高いレベルで遂行することを求められることが多いのではないでしょうか。
誰でもできる仕事ではスキルも上がらずキャリアアップにつながりませんし、全ての業務を高いレベルでやらされたら疲労やストレスが溜まり、離職や二次障害につながってしまいます。
障害者雇用で働く際は、かならず担当する予定の業務が自分と合っているかは確認してください。
あわせて、1年後、2年後に会社が自分にどんな仕事を任せようと考えているかも確認しておいたほうがいいです。確認しておかないと、お互いに「話が違う!」となりがちです。
低賃金
つづいては賃金についてです。障害者雇用の賃金が一般雇用より低いことはネットやSNSの普及でかなり世間的も広まりましたが、障害のある当事者からしたら死活問題です。
厚生労働省の「障害者雇用実態調査」によると、発達障害者の1ヶ月の平均賃金は13万円、週の労働時間が30時間以上の場合は15.5万円です。
この数字を見て、高いと思うでしょうか。地域によっては「こんなもんだろう」と思う方もいるかもしれませんが、首都圏に住む人から見たら激安です。
東京の最低賃金が1163円ですから、1日8時間で月22日働くと20万4800円です。そう考えるとずいぶん安いですね。
障害者雇用の賃金が安い理由は、単純な業務や補助的な業務が多い事による業務内容の限定化、単純労働が多いことが1つの原因です。
低スキルでもできる仕事はたしかに多くの障がい者に任せやすいですが、その分スキルが身に付かず、低賃金のまま給料が上がらない原因になりがちです。
そのほか、賃金が上がらない理由としては、非正規雇用が多いことも大きな原因の1つです。
障害者雇用は一般雇用に比べて離職率が高く、勤続年数も少ない傾向にあります。企業からすると正規雇用してもすぐに離職する労働者はリスクが大きいため、非正規雇用での求人が多いです。
非正規雇用は正規雇用に比べると雇用が不安定で賃金も低いため、結果的に障害者雇用=低賃金となりやすいのです。
福祉的就労との混同
障害者雇用の問題で意外と見過ごされがちなのが、この福祉的就労との混同です。
どういうことかというと、障害者雇用の一般就労と、就労継続支援事業B型、A型事業所の働き方がすべて「障害者雇用」と言う形でひとまとめに語られがちなのです。
障害者雇用の一般就労の場合、雇用契約を結んで非正規、もしくは正規雇用で働くことになります。合理的配慮を除けば一般雇用と働き方はそれほど変わりません。
一方、福祉的就労の場合、就労継続支援B型とA型で大きく働き方が異なります。そもそもB型は雇用契約を結ばずに作業をする場所ですから、厳密にいうと働くというのともちょっと違います。
B型の場合は、作業に応じた「工賃(平均月額:7,000〜15,000円程度)」支給と言う形で、作業を通じて体力維持、生活支援、社会性の向上など社会生活のスキルを身につける場所です。
形としては、労働ではなく福祉的サービスを受けながら作業をしてお金をもらう場所、という理解の方が正しいかと思います。
A型作業所の場合は、雇用契約を結んで働くため、働く地域の最低賃金以上の給与が支給されます。A型の場合は「労働」なので、働きながら就労スキルやマナーの習得、職場適応訓練を行う場所です。
ただ、働くと言っても一般就労への移行を目指すことが目的ですから、働く人の障害や体調に合わせて軽作業や事務補助的な仕事を行うのが中心です。
時給別に並べると、B型作業所は時給200円~、A型作業所が時給900円台(地域別最低賃金)~、一般就労が最低賃金以上、と大きく差があります。
これらすべてをひとまとめにして、「障害者雇用」と呼んでしまうことは働き方や賃金の差などの誤解につながってしまいます。
結局どうすればいいのか
結論から言うと、今まで挙げた課題の解決にきちんと取り組む作業所、企業への就職を目指すことをおすすめします。
障害者雇用や障害者に理解のある企業選び、障害者の強みを活かす業務設計、能力開発によるスキルアップを行っている、きちんとした評価と業務に見合った報酬を支払う制度がある、などです。
実際はこれらの条件をすべて満たす企業はまだまだ少ないのと、条件を満たすような企業はたいがい大企業で入社が難しいのも障害者雇用の課題かと思います。
本来ならすべての障害者雇用を行う企業が障害者に理解があり、障害者雇用にも力を入れているのが理想だと思いますが、企業体力の問題や障害者雇用への意識がまだまだ低いなどハードルは高いです。
もしあなたが障害者雇用での就職を目指される場合は、賃金や労働条件も大事ですが、「障害者雇用に理解のある企業か?」というのを1つ目安にして探してみるとよいかと思います。
それでは。ここまで読んで下さりありがとうございました。↓よかったらポチっとお願いします。今後の励みになります。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村


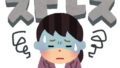
コメント