
日本では「障害者雇用促進法」に基づき、一定規模以上の企業には障害者を雇用する義務が課されています。
2024年4月からは、民間企業における法定雇用率が2.5%に引き上げられ、2026年7月にはさらに2.7%にまで上がることが決定しています。
この流れの中で注目されているのが、障害者雇用担当者という役割です。企業の中で障害者の採用から定着、キャリア支援に至るまでを担うこの仕事には、専門性と人間力が求められます。
この記事では、障害者雇用担当者の主な業務内容、果たすべき役割、そしてこの仕事ならではのやりがいについて、実務の視点からご紹介します。
障害者雇用担当者の業務内容①採用
まず最初のステップは「採用」です。障害のある求職者を対象に、適性に合った職種や配属先を見極め、応募から入社に至るまでをサポートします。
実際の仕事は人材紹介営業とか、人事の中途採用と似てるかもしれません。
ざっとやることを書くと、こんな感じです。
- ・応募者の母数形成
- ・障害者雇用に特化した求人票の作成
・ハローワーク、就労移行支援事業所、大学などとの連携
・面接・職場見学の調整
・採用選考における配慮事項の確認と調整
・入社前の職場環境整備(バリアフリー化、業務マニュアル整備等)
応募者の母数形成と言うのは、簡単に言うと求人に応募してくれる人を増やすための取り組みのことです。
広告を打つ、求人票を色々な媒体に掲載する、障害者雇用で働きたい人向けに説明会を開く、などなど。
いくら会社が働きやすい環境を整えても、会社の名前を知ってもらわなければ誰も応募してくれません。
知名度の高い大企業なら何もしなくても何百人と応募が来ますが、ほとんどの企業は何らかの形で母数形成を行う必要があります。
求人票の作成というのは、読んで字のごとくです。会社の紹介や募集職種、労働条件などを書いた求人票を作るお仕事です。
給料や年間休日と言った部分は一担当者の力ではどうにもなりませんが、会社のPRや働きやすさのアピールの部分は意外と自由に決められます。
例えば、正社員登用制度あり!とか、勤続〇年以上の社員多数!みたいな感じで働きやすさをアピールします。
障害者雇用の採用は年々競争が激しくなっているので、魅力がないと思われたら全然応募が来ません。マジです。
他社に負けないようにあの手この手で自社の魅力を伝えないといけないのですが、そのうちの1つが求人票というわけです。
私も日々他社の求人票を検索して勉強してたりします。
障害者雇用の応募者を増やすには、地道なコネ作りも大切です。ハローワークや就労移行支援事業所などにも足しげく通っています。
電話でアポを取り、自社の情報提供を行い、「うち、こういう会社なんですけど、応募してくれそうな人いませんかね・・・?」と頭を下げる事もあります。
私の会社は障害者雇用にそれなりにきちんと取り組んでる(と思いたい)ので、営業をかけて邪険に扱われたことは一度もありません。
地道にドサ回りをしていると、ふとしたタイミングで「実は御社に応募したい利用者さんがいるんですが・・・」と連絡をくれたりします。
今まで採用した人の2~3割は人材エージェントではなく紹介経由です。障害者雇用では横のつながりがとても大切だったりします。
採用担当者は応募者を増やすだけでなく、会社説明会や面接も行います。
説明資料の作成、応募者との連絡調整や当日のアテンド、面接官まで何でもやります。「なんでも屋」という言葉がぴったりの仕事だと自分でも思います。
採用が決まった場合、所属部署ともやり取りして、定着支援のための調整を行います。
ですので、メール、電話、対面/オンラインの会議がひっきりなしにあります。1人雇用するために平均5~10人以上の関係者とやり取りします。
人と話したり連絡、調整する機会が多い仕事ですので、対人業務が苦痛な方にはキツイと思います。
その代わり事務スキルはそこまで高度な物は求められません。Excelでマクロ組むとか、データ分析みたいな業務はほぼありません。(できればもちろん便利)
障害者雇用担当者の業務内容②定着支援
障害者雇用担当者の大事な仕事その②は、定着支援です。
簡単に言うと、雇用した障害者社員が辞めないようにサポート・フォローするお仕事です。
具体的には定期的な面談、メンタル面や業務面のフォロー、職場の人間関係やコミュニケーションの取り方について相談に乗ったりします。
採用の段階で希望される合理的配慮やご本人の障害特性については確認しますが、実際に働き始めると面接や書類では確認できなかった課題が現れることがあります。
その場合は課題の種類や内容に応じて、障害者社員本人、配属先の指導担当者や上司と一緒に課題の共有と解決のための話し合いを行います。
一番多いのは人間関係の課題で、次は業務上の課題です。
人間関係だと言い方がキツイとか、忙しくて話しかけづらい、みたいな内容が多いです。業務上では指示が理解できない、業務量やレベルが合っていないという訴えが多いです。
こういう場合は障害者社員だけでなく、相手方の意見も必ず聞く必要があります。どちらが正しい/悪いではなく、どうすれば問題なく業務を行えるようになるか?の視点が重要です。
対応も1人1人異なり個別性が高いため、採用に比べるとかなりスキルが求められます。私も日々新しい支援技法を身につける為勉強しています。
障害者雇用担当者の業務内容③社内啓発
さて、3つ目のお仕事は社内啓発です。
これはどんなお仕事かと言うと、職場や社員全体に障害者雇用の理解や受け入れを促進するための活動です。
そもそも会社や部署、社員が障害者や障害者雇用の理解がないと、障害者雇用は絶対上手くいきません。
障害者雇用の理解がないパターンだと、とある部署に「障害者雇用の方の受け入れをお願いできませんか?」というと「うちじゃ無理です」と即答されたりします。
または、「健常者並みに仕事ができる身体障害者ならいいよ」とか言われることもあります。何十年前の時代じゃコラ、とつい言い返したくなります。
いくら障害者雇用のために環境整備や職務切り出しを行っても、肝心の職場や人の受け入れ態勢が整っていないと、結局障害者社員はいづらくなってやめてしまいます。
そうならない為にも、社内研修や啓発活動に力を入れる必要があるのです。
具体的には全社員向けの障害者雇用理解促進の研修開催、社内イントラネットでの情報発信、役員向けに資料作成、提出、人事制度の改善なんかを行います。
30年前はそれこそ障害者雇用といえば身体障害者の方がメインでしたが、現在の労働市場のメインは精神・発達障害者です。
いい悪いという話ではなく、市場のボリュームゾーンが精神・発達障害者である以上、採用ターゲットもアプローチの仕方も昔とは異なります。
もちろん障害特性や配慮内容も異なりますから、「今の障害者雇用はこういう人たちが中心で、活躍してもらうためにはこんな取り組みが必要です」ということを伝える必要があります。
研修や啓発活動を通して、会社全体が障害者雇用に前向きになるよう、風土作りをするのも障害者雇用担当者の大切な仕事です。
障害者雇用担当者のやりがい
ぶっちゃけ、障害者雇用担当者はニッチな仕事です。今はネットで「障害者雇用担当者」と探せば求人が出てきますが、表に出ていない求人の方が多いと思います。
私はこの仕事が好きでやっていますが、正直楽な仕事ではありませんし、給料も高くありません。もっと楽に稼げる仕事はいくらでもあります。
ではこの仕事のどこにやりがいがあるのか。まず1つ目は、専門性が求められることです。
最低でも身体・知的・精神・発達障害の障害特性と基本的な配慮事項、どんなことが職場の困りごとになりやすいか知らないと仕事になりません。
領域的には医療・福祉・人事・法制度・キャリア開発など幅広い知識と経験が求められます。
今まで取得した国家資格の勉強や実務で得たスキルを活かせるので、専門性を活かしてキャリアップしたい方にはおすすめです。
そのうえで、それぞれの障害者ごとの特性と業務内容、職場環境にあわせた個別対応が求められます。
業務を行う上で事前に専門知識と経験が要求されますので、いきなり未経験から転職するのは難しいと思います(転職できてもその後が大変です)
もし障害者雇用担当者をやりたい場合は、福祉施設や就労移行支援事業所などで働いてから転職するか、企業の人事担当者からキャリアチェンジするのがいいかもしれません。
職務遂行のハードルが高い分、適切な対応ができた時には達成感があります。
障害者社員からは「Kさんのおかげで自信をもって働けるようになりました」と言われたり、受け入れ部署からも「いい人を紹介してくれて助かっています」と感謝されると嬉しくなります。
ただ感謝されるだけでなく、仕事上で障害者社員がいる他部署に用がある時も優先して助けてくれたり頼みごとがしやすくなります。
担当する障害者社員が増えれば増えるほど社内のコネも広がるので、最近は障害者雇用以外の仕事もしやすくなりました。
障害者雇用担当者は人の成長や変化に立ち会えるだけでなく、専門性を活かして実務にも活かせる魅力ある仕事です。
単に障害者社員を支援するだけでなく、会社の法定雇用率達成や社会的責任への貢献と言う意味でも、会社全体への影響力が大きい役割となります。
いかがでしたでしょうか。この記事で障害者雇用担当者の仕事に少しでも興味関心を持って頂けたら幸いです。
それでは。ここまで読んで下さりありがとうございました。↓よかったらポチっとお願いします。今後の励みになります。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

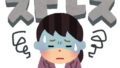

コメント