―開示したことで、閉じられた未来―

1. 「障害をオープンにしてください、サポートしますから」
弊社では、障害をオープンにした就労を推進しています。
「安心して働ける環境づくり」を謳い文句にしています。
求人票には「合理的配慮を行います」「障害者雇用促進中」とデカデカと書く。
ええ、それは間違っていません。
でも、本音を言うとですね、オープンにしてくれたほうが管理がしやすいんですよ。
「何ができないか」「どんな制約があるか」事前に聞けますから。
つまり、「あなたにはこの範囲で働いてもらいます」という線引きが最初からできる。
当人も「配慮を受けた」と思ってくれるし、企業も「事故防止」ができる。
ウィンウィンです。
……建前では。
2. 「採用ハードルは上げません、でも範囲は狭くなります」
「障害をオープンにしてもらえれば、特性に合わせた仕事を用意します」と言います。
ですが実際には、できる仕事はだいたい単純作業です。
責任や裁量が伴う仕事は「リスク管理上、難しい」と判断します。
それを「合理的配慮」という言葉で包むんです。
「無理をさせない」「負担を減らす」。
そう言えば聞こえはいい。
本人も「そうか、ここなら安心だ」と思ってくれるでしょう。
でも同時に、その時点でキャリアの選択肢はごっそり減るんです。
「将来のキャリアを見据えて」とか「成長をサポート」とか、求人票には書いてますけどね。
そこに辿り着ける人はごく一部です。
3. 「“開示したから配慮を受けられる”は嘘じゃない」
誤解しないでください、ウソはついていません。
開示してくれたら、配慮はしますよ。
でも配慮できる範囲は「企業が決める」んです。
例えば、勤務時間を短縮する。
作業を単純化する。
責任を軽くする。
それで「職場定着」を目指す。
でもね、それは「本人が成長する」こととは別です。
成長機会を奪う「優しい牢屋」になっていることも多いんです。
でもそれは企業の責任じゃない。
「本人が希望した配慮」だから。
4. 「オープンにしたことで広がった未来もある?」
もちろん成功事例はあります。
それを広報で大きく取り上げます。
「障害を開示し、配慮を受けて、見事キャリアアップ」
「周囲の理解で定着」
でも冷静に見れば、そういうケースは「もともと特性が軽度」「職場に都合のいい特性」の場合が多い。
現場だって「できるだけ自立してほしい」という要望がある。
要するに「開示しても受け入れてもらえる人」と「開示したら選択肢が狭まる人」がはっきり分かれる。
でも広報ではそれを言いません。
「開示を勧める理由」は言うけど、「開示したことで閉じられる未来」までは触れない。
それを言ったら制度設計そのものが問い直されますからね。
5. 「安心して働ける、の正体」
「オープン就労を進めます」
「配慮します」
「安心です」
はい、全部事実です。
ただし、その「安心」は当事者のキャリアを狭めることでもある。
責任を負わなくていい代わりに、裁量も成長も手放してもらう。
本人の同意を得た形で。
そしてもし「物足りない」「成長したい」と声をあげたら?
「それは難しい」と答えます。
「あなたの特性を理解して、無理をさせないため」です。
優しいフリをして、選択肢を絞る。
開示させて、リスクを管理する。
それが“合理的配慮”のもう一つの顔。
そしてそれこそが企業が「安心して障害者を雇える」仕組みなんです。
開示すれば安心できる?
それは安心という名の囲い込みかもしれません。
でも私たちはちゃんと「配慮しています」と言えますから。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

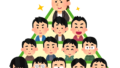
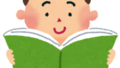
コメント