
――やる気がない? いや、“余力”がないだけです。
1.【初回面談】
最初はね、ちゃんと希望もあったんだよ。
ネットで「就労移行」「定着支援」「福祉の力で自立を」って言葉見て、
「あ、ここならなんとかしてくれるかも」って思っちゃったんだよ。
で、支援機関に行ってみた。
支援員はやさしそうにうなずいてくれたし、
「一緒に頑張りましょう」なんて言ってくれてさ。
こっちはギリギリの精神状態で、
それでも“ここで人生変えたい”って思ってたのにね。
2.【見えない序列】
ところが通い始めてすぐ気づく。
支援機関の中には、“わかりやすく優先される人間”がいる。
・発言が多くて明るい人
・資格を取ろうとしてる人
・職歴がある人
・相談内容が「やる気」に満ちてる人
で、俺みたいに
・短期離職多くて
・コミュ障で
・喋るのもしんどくて
・朝も起きれなくて
…ってタイプは、だんだん支援員の対応も雑になる。
「○○さんは頑張ってるのに、あなたはどうするの?」って、
ああ、比較される側か、俺。
3.【相談という名の査定】
何回か面談重ねると、
もう“相談”じゃないんだよな。
「次は何を目標にしますか?」
「このままだと訓練の意味がないですよ」
「もう少し積極的に動かないと就職は難しいです」
こっちだってわかってるんだよ。
でもな、動けない。
“動けない理由”を相談したくて来てんのに、
返ってくるのは「もっと動け」って指示だけ。
支援じゃなくて、評価。
ああ、ここも「動ける人間だけが救われる場所」なんだなって、
日に日に実感する。
4.【“不良在庫”扱いのリアル】
そうやって通ってるうちにさ、
他の人はどんどん実習に行ったり、就職が決まったりする。
で、俺はというと、
「実習先が見つからないですね」
「受け入れ先がないですね」
そりゃそうだろ。
短期離職、空白期間、資格なし。
ついでに、発達特性あってマルチタスクも苦手で、
電話も怖いし、人と喋るのも疲れる。
誰が雇うんだよ。
誰も拾わねえよ。
支援員だって、最初は「一緒に考えましょう」って言ってたけど、
ある時を境に、「様子見ましょうか」って言い出す。
これ、福祉用語で言うところの「詰み」ね。
5.【最後は自己責任】
で、半年、1年、2年経っても決まらないとさ、
もう「就労意欲がない」「継続支援が難しい」って扱いされるんだよ。
え? 俺が?
「意欲がない」って言うけどさ、
“意欲”って、物理的に湧かないもんなんだよ。
絶望が積もりすぎてんの。
でも制度上は、“努力不足の利用者”ってことになる。
記録には「支援提供したが改善見られず」って残されて、
はい、次の利用者どうぞーって回されて終わり。
支援機関だって実績が大事だからね。
就職した人=成果、残った人=在庫。
俺はその後者。
人間じゃなくて、“失敗案件”。
■結局:支援って、誰のためのもの?
ほんとの支援って、「動けない人間」こそ支えなきゃじゃないの?
でも現実は、「動ける人だけが加点されて、動けない人は切り捨てられる」っていう、
支援の皮をかぶった選別システム。
俺らが欲しかったのは、
“導く人”じゃなくて、“寄り添う人”だったんだけどな。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村


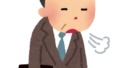
コメント