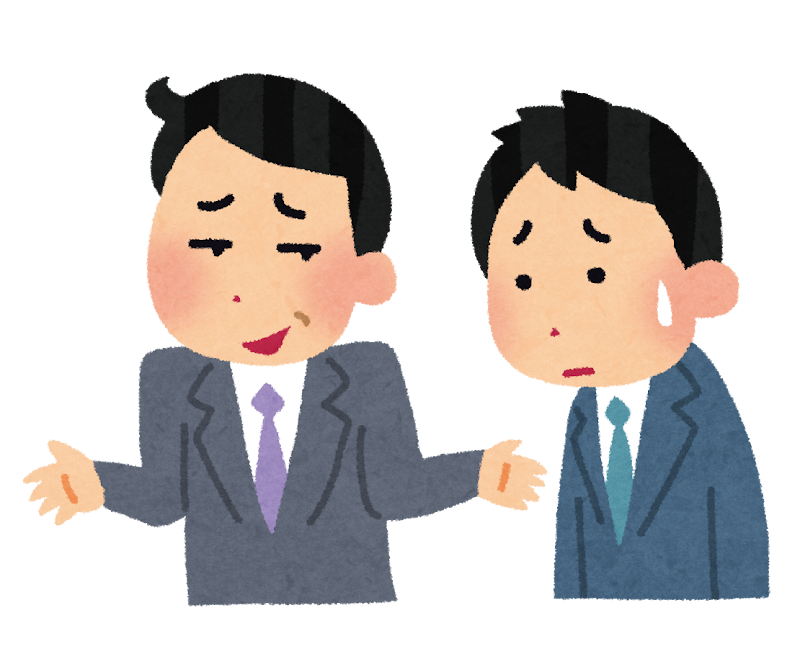
こんにちは。「ASD(自閉スペクトラム症)は“嫌われ病”である」。そんな表現を耳にして、心がざわついた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私は、この言葉の裏に潜む社会の不寛容さや、当事者が背負っている見えない苦労にこそ、私たちが目を向けるべきだと感じています。
「嫌われる」という現象には、本人の言動の問題だけではなく、それを受け取る側の思い込みや偏見、そして社会全体の構造が関係しています。そして実は、この“嫌われ病”という言葉は、ASD当事者の中から生まれたものでもあるのです。「自分は頑張っているのに、なぜか嫌われる」。そんな悲しみや諦めが凝縮された言葉でもあります。
では、なぜASDの人が「嫌われやすい」と感じられてしまうのか? 本当にそうなのか? その理由と誤解を、私なりに紐解いていきたいと思います。
コミュニケーションのズレが人間関係を壊してしまう
ASDの方に多く見られる特性のひとつが、「対人コミュニケーションの難しさ」です。たとえば、相手の表情や声のトーンから感情を読み取ることが苦手だったり、会話の文脈から“空気”を察することが難しかったりします。悪気はまったくないのに、「なんでそんなこと言うの?」「ちょっと感じ悪いな」と思われてしまうことがあるのです。
この“ズレ”は、相手にとってはストレスとなり、いつしかその人自身への苦手意識や敬遠につながってしまいます。ASD当事者の方も、自分の発言で人間関係が壊れていく経験を何度もしており、「自分が原因なんだ」と自己否定に陥ることも少なくありません。
大切なのは、「その行動には理由がある」という理解です。ASDの人が“空気を読まない”のではなく、“空気を読み取る情報処理の仕方が異なる”という点に、周囲が気づけるかどうか。そこに共感と配慮の入り口があります。
「共感の仕方が違う」だけで、こんなにも誤解される
ASDの方は、「共感性が低い」と言われることがあります。ですが、これは大きな誤解です。共感の“感じ方”や“表現の仕方”が一般とは違うというだけなのです。
たとえば、友人が落ち込んでいるとき、多くの人は「それはつらかったね」と感情を共有しようとします。
一方で、ASDの方は「それならこうすれば解決できるよ」と論理的な提案をしがちです。気持ちを軽視しているわけではなく、むしろ“どうすればいいか”を必死に考えているのです。
でも、相手にとっては「気持ちをわかってくれない」と感じてしまう。これが、ASDの方が「冷たい」「自己中心的」と誤解される根っこにあるのだと思います。そうやって少しずつ距離を取られてしまうことが、“嫌われやすさ”につながっているのです。
重要なのは、「共感にも多様性がある」という視点です。人それぞれに違った共感のスタイルがあっていい。そのことを、もっと多くの人が知るべきだと私は思います。
社会の「普通」は、誰のものか
さて、ここで私たちが見直すべきなのが、社会の「常識」という名のルールです。日本社会はとても“同調圧力”が強い文化を持っています。「空気を読む」「和を乱さない」「言わなくても分かる」。こうした“暗黙の了解”が尊ばれる中で、ASDの方は無意識のうちに排除されやすい状況に置かれてしまいます。
ASDの人は、明確なルールや構造化された環境には強い傾向がありますが、曖昧な指示や、空気を読む文化には大きな負担を感じます。にもかかわらず、そのズレを「個人の欠点」として扱ってしまう社会の在り方こそが、ASDの人を“嫌われる存在”へと押しやっているのではないでしょうか。
ここで私が言いたいのは、「普通」に疑問を持とう、ということです。多数派の感覚だけを“正解”として押しつけるのではなく、多様な感覚の共存を当たり前にする。その視点があれば、ASDの人に対する評価も変わってくるはずです。
「嫌われ病」の認識に対して、周囲ができること
ASDを「嫌われ病」と呼ぶ風潮の根底には、理解不足とコミュニケーションのすれ違いがあります。でも、それは変えられます。変えていけるのです。ASDの方は「人を困らせたい」わけではありませんし、「わがままに振る舞っている」わけでもありません。むしろ、社会に適応しようと必死に努力しています。
なのに、その努力が見えづらく、伝わりづらいからこそ、誤解されてしまう。ここを周囲が理解し、寄り添うことで、「嫌われる人」から「理解される人」へと変化は起こります。
私たち一人ひとりが、少しだけ感受性の幅を広げること。ちょっと立ち止まって、「この人にはこの人なりの理由があるかもしれない」と思ってみること。それだけで、ASDの人が感じている孤独や疎外感はぐっと軽くなるはずです。
おわりに──共感とは「同じ」じゃなく「違いを知る」こと
ASDが「嫌われ病」と言われる社会は、正直に言って、まだまだ未熟です。でもそれは、誰かが悪いわけではなく、“知らなかっただけ”なのだと私は思います。
知らなかったから、理解できなかった。理解できなかったから、距離を置いてしまった。だからこそ、今ここで「知る」ことに意味があります。
共感とは、「同じように感じること」ではありません。「違うことを知ること」でもあるのです。そう思える人が一人でも増えていけば、ASDの方が生きやすくなるだけでなく、社会全体もやさしく、しなやかになっていくのではないでしょうか。
違いを“問題”ではなく、“多様性”として捉えることで、ASD当事者と周囲の相互理解につながるのではないでしょうか。
ここまで読んで下さりありがとうございました。↓よかったらポチっとお願いします。今後の励みになります。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村



コメント